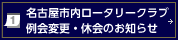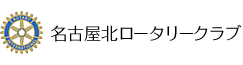 |
|
 |
 |
2020年6月5日(金)
 6月12日(金)より通常例会に戻ります。岡部ガバナーエレクトのご挨拶、また新入会員の会長ゲストとしてのご参加も予定しております。皆様ご無理のない範囲でご出席下さい。
6月12日(金)より通常例会に戻ります。岡部ガバナーエレクトのご挨拶、また新入会員の会長ゲストとしてのご参加も予定しております。皆様ご無理のない範囲でご出席下さい。
さて、古代インドでは人生の過ごし方についての法則がありました。人の一生を4つの大きな括りに分け、そしてその時期やその時期の生き方について「あなたは今、人生のこの時期だからこう生きなさい」と知恵を示したのです。その法典は「マヌ法典」というものです。紀元前200年から紀元後200年の間に成立したものと推定されていますが、この法典では人生を4つに分ける「四住期(しじゅうき)」という考えが明記されております。その4つとは「学生期(がくしょうき)」、「家住期(かじゅうき)」、「林住期(りんじゅうき)」、「遊行期(ゆうぎょうき)」の4つです。そしてそれぞれの期間は次のように定義付けられています。まずは「学生期」。これは年齢的には0歳~24歳までで、誕生して人間としての生きる知恵をつけるための学びの時期とされます。次に「家住期」。これは25歳~49歳までで、社会人として伴侶を得て家庭を作り仕事に励むという人生で最も充実した時期です。そして3番目は「林住期」。これは50歳~74歳までで、仕事や家庭から卒業し林に庵(いおり)を構えて自らの来し方・行く末を深く瞑想する時期とされます。いわば第二の人生の充電期といっていいと思います。そして最後の「遊行期」。75歳~100歳までで、林(つまり庵)から出て思うままに遊行して人に道を説き、人生の知恵を人々に授ける時期としています。日本では今「人生80年」と言われていますので、この4期の年齢区分を1期20年として換算しますと、多少の差異はあるかもしれませんが、この頃はさらに「人生100年」と取り沙汰されるようにもなってきていますので、だいたいはこの年齢区分で通ずるかと思います。こうした区分からみますと、私たちロータリーの会員の方々はだいたい「林住期」か「遊行期」とりわけ「林住期」(50歳~74歳に当たる方が多いかと思いますが、いかがでしょうか?)
こうした古代インドの知恵、人生論は一聴に値するものと思います。50歳~75歳…、社会人として務め、あるいは務めを終えた後のすべての人が迎える最も輝かしい第三の人生「林住期」は人生の黄金期でもあります。一生働くだけの人生などという愚を避け、人生の黄金期、収穫期といいますか、人生のクライマックスを「林住期」という第三の人生において心ゆくまで生きるのが人間らしい生き方なのだというわけです。林住期は、これまで蓄えてきた体力、気力、経験、キャリア、能力、センスなど自分が磨いてきたものを土台にしてジャンプする時間を取り戻す季節であり、人生におけるジャンプ、離陸の季節でもあります。林住期はやりたいことをする…人生二毛作などといった言葉が囁かれるのもむべなるかであります。しかし、老後を自由に生きる「林住期」と死を見つめる「遊行期」という人生後半の生き方はとかく難しいものです。世間では老いるということが不快な現象のように語られます。そしてそれに対する切ない反抗が「アンチエイジング」などという表現です。年を取る、老いるということは、佇まいが静謐(せいひつ)になること、無常を受け入れることといった見方もあります。かの吉田兼好は、死の訪れ方についてこう言っています。「死は前よりきたらず」「かねてうしろにせまれり」。つまり、死は前の方から徐々に近付いて来るのではなく、背後からぽんと肩を叩かれ不意に訪れるものだと。人生の余白でもある「遊行期」の段階でどう人生を締め括るか、一生を総括する事の難しいことはいうまでもありませんが、こういう辞世があります。「六(ろく)でなき仕事も既にやり終えて先立つ妻に会うぞ嬉しき」。これはかの清水次郎長の辞世です。東海道の大親分として名を馳せた次郎長ですが、生き尽くした感慨は伴侶への思い入れでした。こんな歌を詠まれて、お蝶さんもさぞ浮かばれたことでしょう。

- 今月はロータリー親睦活動月間です。
- 本日は、Eクラブ方式の例会といたします。
- 異動により、亀井昭男さんが3月6日、水谷 仁さんが3月末日、
北﨑 潤さんが4月1日を以って退会されました。 - 令和2年6月1日より、ドル換算レートが1ドル108円(現行107円)に変更との通知がございましたのでお知らせいたします。
- 次週6月12日(金)より、名古屋東急ホテル(3階ルネッサンスの間)で通常例会を再開いたします。例会に出席される方は、マスクの着用、手指の消毒等の徹底を、当日体調のすぐれない方は、例会への出席を見合わせていただきますようお願いいたします。
- 本日13時30分より、本年度最終理事会をZOOMにて開催いたしますので、理事役員の方々はご参加くださいますようお願いいたします。
- 他クラブの動き
※現在、多数のクラブが通常例会でのビジター受付を取り止めております。
他クラブの例会でビジター参加を希望される際は、事前にクラブへご確認ください。- 通常例会(ビジター受付なし)のお知らせ
6月 8日(月) 名古屋東RC
6月 9日(火) 名古屋名東RC、名古屋名南RC、名古屋錦RC
6月10日(水) 名古屋和合RC
6月15日(月) 名古屋東RC、名古屋中RC、あまRC、名古屋栄RC 名古屋昭和RC
6月16日(火) 名古屋RC、名古屋名東RC、名古屋千種RC、名古屋錦RC、
名古屋城北RC
6月17日(水) 名古屋南RC、名古屋アイリスRC
6月18日(木) 名古屋東山RC
※通常例会となりますが、ビジターは例会に参加できませんので、お間違えの
ないようお願いいたします。 - 例会変更(サイン受付なし)のお知らせ
名古屋守山RC 6月17日(水) 夜間例会のため
名古屋和合RC 6月17日(水) 春の家族会のため
名古屋名駅RC 6月17日(水) 短縮例会のため
名古屋丸の内RC 6月18日(木) 例会場変更のため
※例会変更となりますが、サイン受付はございませんので、お間違えのないよう
お願いいたします。 - 例会休会のお知らせ(サイン受付はございません)
6月10日(水) 名古屋名駅RC
6月15日(月) 名古屋空港RC
6月16日(火) 名古屋名南RC
6月18日(木) 名古屋西RC、名古屋瑞穂RC、名古屋大須RC、名古屋葵RC
- 通常例会(ビジター受付なし)のお知らせ
名古屋北ロータリークラブ フォーティーンヒルズセンタービル604号室 |